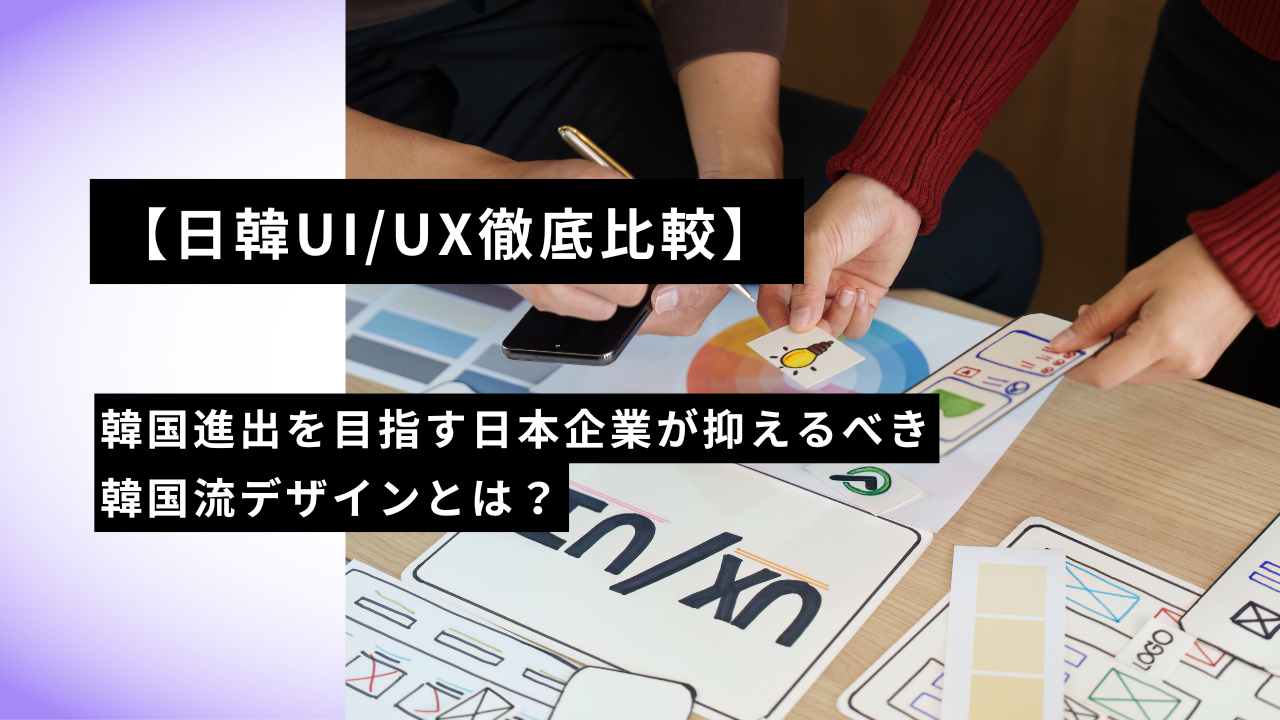韓国市場への進出を目指す日本企業にとって、現地ユーザーの嗜好に合わせたUI/UXデザインの最適化は成功の鍵となります。地理的に近く文化的な交流も盛んな韓国ですが、デジタル製品・サービスのデザインやユーザー体験には日本と異なる傾向が存在します。本記事では、日韓におけるUI/UXデザインの違いをデータと事例に基づき徹底比較し、韓国進出時に押さえるべき「韓国流デザイン」のポイントを解説します。事実に基づいた正確な情報をもとに、韓国市場でユーザーに響くUI/UX戦略を探っていきましょう。
1. 日本と韓国のUI/UXデザインは何が違うのか?
まず、日本と韓国でウェブやアプリのデザインにどのような違いがあるかを整理します。
文化や言語の違いがUI(ユーザーインターフェース)デザインにも表れており、以下の点が主な相違点です。
言語と文字表現の違い: 日本語は漢字・ひらがな・カタカナという3種類の文字を組み合わせるため、画面上で自然にメリハリが生まれデザイン性が高くなります 。
例えばバナー画像でも文字にバリエーションが出やすい傾向があります。
一方、韓国語(ハングル)は表音文字のみ、中国語は漢字のみと一種類の文字体系で統一されているため、文字だけでは変化が付きにくい特徴があります 。
そのため韓国ではフォントサイズや太さを変える工夫で強調を行いますが、日本のバナーに比べると文字要素だけでは地味に見える場合もあります 。
実際、中国・韓国のサイトは日本に比べシンプルなタイポグラフィに感じられることが多いです。
情報量とビジュアル重視のバランス

日本のウェブデザインは必要な情報を盛り込みつつもビジュアルとの調和を図る傾向がありますが、韓国のデザインはビジュアル優先のアプローチが顕著です。
韓国ユーザーは視覚的に惹きつけられることを好むため、サイトを開いてわずか数秒(約3秒)以内に目を引くような強いビジュアル要素が重視されます。
その結果、韓国では大胆な画像と短いキャッチコピーのみで世界観を伝えるようなシンプルなデザインが多く、テキストは必要最低限、レイアウトも余白を大きく取るのが一般的です。
逆に日本のサイトは、ユーザーに豊富な情報を提供する意図からテキストやリンクを多めに配置するケースも見られます。
例えば同じブランドのキャンペーンページでも、韓国版は大きなビジュアルと簡潔なコピーのみで訴求し、日本版は詳細な説明や複数のバナーを盛り込むなど情報量が多い傾向があります。

韓国(左)と日本(右)の「31アイスクリーム(Baskin Robbins)」公式サイトの比較例です。
韓国サイトでは大きな画像と「Wonder」というキャッチコピーだけでキャンペーンを表現しており、余白も多く取られている。一方、日本サイトでは「最大10コ選べるチャンス!」といった大きな文字情報や複数の商品の写真、メニュー項目などが配置されており、より多くの情報を一画面に提供しています。
こうした違いからも、日本より韓国の方がビジュアル重視・情報簡素化の傾向が強いことがわかります。
色使いと強調方法の違い: 韓国のUIデザインでは派手な色彩よりも統一感や清潔感が重視され、テキストを色付けして強調することは多くありません 。強調したい部分は太字や大きめのフォントで示し、全体の色調は抑えめにしてあります 。
代わりに、画像自体の彩度やコントラストを上げて目を引く工夫が凝らされ、写真やビジュアル要素で鮮やかさを演出するのが特徴です 。一方、日本のデザインでは重要なテキストに色を付けたり装飾したりする例も少なくありません。韓国ではまた、硬い印象を避けるためイラストが頻繁に使われます。特に手書き風のゆるいイラストは親しみやすさを生むため好まれ、デザインに遊び心や余裕を与える効果があります 。日本でもイラストを用いる場合がありますが、韓国ほどその比率は高くないようです。
以上のように、日本と韓国ではUIデザインのアプローチに明確な違いがあります。日本企業が韓国向けサービスを提供する際は、「文字で伝える日本」から「ビジュアルで魅せる韓国」へ発想をシフトすることが求められます。ただし、ビジュアル重視といっても単に派手にすれば良いわけではなく、次章以降で述べるように韓国ユーザーの文化的背景やデジタル行動に根ざしたデザイン戦略が重要です。
2. 韓国ユーザーのデジタル行動と嗜好の特徴
UI/UXのローカライズ戦略を立てるには、現地ユーザーの行動特性を理解することが不可欠です。
韓国の消費者はデジタル環境においていくつか日本とは異なる特徴を示しています。
モバイルファースト志向とオムニチャネル
韓国は世界有数のモバイル大国であり、EC(電子商取引)も圧倒的にスマートフォン経由で行われています。実際、韓国ではEC取引の72%以上がスマホ経由とされ、購買行動もすっかりモバイルファーストに定着しています。スマホで手軽に買い物が完結する環境にユーザーが慣れているため、企業側もまずモバイルで快適なUI/UXを提供することが前提となります。
またオムニチャネル戦略の浸透度も高く、実店舗とオンラインストア、モバイルアプリがシームレスに連携した購買体験が当たり前になりつつあります。例えば店舗在庫のリアルタイム確認や、オンライン注文商品の店舗受け取り、アプリ経由の会員サービスなど、チャネル横断で一貫したユーザー体験を提供している企業が多いです。
このような背景から、韓国向けUI/UX設計ではスマホでの操作性最優先かつオフラインとオンラインの連携を意識した設計が重要です。
トレンドへの敏感さとSNS活用
韓国の消費者、とりわけ若年層は流行に対する感度が非常に高く、最新トレンドや新商品情報を常に追いかける傾向があります。SNS(ソーシャルメディア)利用率も高く、商品・サービスの情報収集や口コミ共有にTwitter(X)やInstagram、YouTubeなどが日常的に活用されています。
韓国では有名人やインフルエンサーの影響力が強く、人気インフルエンサーが紹介した商品が瞬く間にヒットすることも珍しくありません。そのため、企業側はUI/UX上でもSNSとの親和性を高める工夫が求められます。具体的には、コンテンツがユーザーにシェアされやすいようビジュアルを工夫したり、口コミやレビューを見やすく配置したりすることが効果的です。
また、韓国の若者は自分がトレンドを作るというより「流れに乗っている」と感じる人も多いという調査もあり、流行していること自体に価値を感じる傾向があります。裏を返せば、「今これが人気」「話題沸騰中」といった演出がユーザーの興味を引きやすいということです。従って韓国向けのUI/UXでは、新着情報や人気ランキング、期間限定キャンペーンなどトレンド要素を前面に出すことが有効でしょう。
国内プラットフォームとライブコマースの隆盛
韓国ではGoogleやYahooではなく、ネイバー(NAVER)やカカオといった国内プラットフォームが日常に深く根付いています。検索もネイバー、メッセージはカカオトークというユーザーが多く、これらプラットフォームとどう連携するかも考慮が必要です。
また近年はライブコマース(ライブ動画配信によるEC)が飛躍的に普及しており、NAVER Shopping LiveやCoupang Liveといったサービスでリアルタイムに商品を紹介しその場で購入できる仕組みが人気です。動画ストリーミングを通じて双方向コミュニケーションを取りながら買い物できる体験は、日本ではまだ新しいですが、韓国ユーザーには「当たり前」の選択肢になりつつあります。
このように、韓国のユーザーは非常にインタラクティブでリッチな購買体験にも慣れているため、単なる静的なウェブページよりも動画やアニメーション、リアルタイム要素を取り入れることで興味を惹きつけやすくなります。
ユーザーの期待値と要求水準
韓国消費者はサービス品質にも厳しく、レビューへの反応やカスタマーサポート対応の速さにも高い期待を寄せています。商品購入後の返品率が日本より高めというデータもあり、逆に言えば「期待と違った」場合にすぐ返品・交換が行われる文化です。そのため企業側は、誇張のない正確な商品説明や丁寧なユーザーサポート対応を用意しておく必要があります。
UI/UX面でも、問い合わせがしやすい導線を設けたりFAQを充実させたりといった安心感を与える設計が大切です。また、韓国市場では競合がひしめきサービスレベルの競争も激しいため、少しでも不便さがあるとユーザーが離れてしまう傾向があります。日本では許容される細かな不便でも、韓国では致命的になりかねません。その意味で、ユーザーからのフィードバックを素早く収集しUI/UXに反映していくアジャイルな改善も求められるでしょう。
以上の点から、韓国のユーザーは「モバイル中心」「トレンド志向」「双方向コミュニケーション重視」「サービス品質に敏感」とまとめられます。では、こうした特徴を踏まえて具体的に日本企業は韓国向けUI/UXをどう設計すべきか、次にポイントを解説します。
3. 韓国向けUI/UXデザイン戦略のポイント
韓国市場でユーザーに受け入れられるUI/UXを構築するために、日本企業が押さえるべき主なポイントをまとめます。先述のデザイン比較やユーザー特性を踏まえ、以下の項目に留意すると良いでしょう。
モバイルファースト設計
スマートフォンでの見やすさ・使いやすさを最優先にデザインします。
画面サイズに最適化されたレイアウトやフォント、指でタップしやすいボタン配置、スクロール操作の快適さなど、モバイルUIの基本を徹底します。韓国ユーザーはPCよりモバイルで買い物・閲覧する比率が非常に高いため、PC版の後追いではなくモバイルを主軸に置いた設計が必要です。
また、ページ表示速度にも注意しましょう。高速通信環境が整う韓国ではページ読み込みが遅いと感じればすぐ離脱されてしまう可能性があります。
ビジュアルで訴求しテキストは簡潔に
「パッと見て魅力が伝わる」デザインを心がけます。
トップページやランディングページでは、高解像度でインパクトのある画像や動画背景を用いてユーザーの目を引きます。キャッチコピーは短く分かりやすくし、説明文は可能な限り削ぎ落とします。詳細な情報は別ページ(商品詳細ページなど)に譲り、ファーストビューでは視覚的インパクトを優先する構成が有効です。
ただし、テキストを減らす分、言葉選びには配慮しましょう。韓国語で違和感のない表現になっているか、文化的に適切かを現地の人に確認することが重要です。
現地言語・文化へのローカライズ徹底
表記の韓国語化はもちろん、ネイティブが見て自然な言い回しになっているか注意します。
「直訳」では微妙なニュアンスが伝わらないため、専門の翻訳者や現地スタッフによるチェックが欠かせません。例えばボタンの文言ひとつとっても、日本的な表現をそのままハングルにするのではなく、韓国のサービスで一般的な言い回しに合わせるとユーザーにとって親しみやすくなります。
また、画像に含まれる文字(バナーのキャッチコピー等)も韓国語版ではフォントやデザインを現地のトレンドに合わせて作り直す方が効果的です。文化的な配慮も必要で、例えば色使いひとつでも国ごとの好みがあります。韓国ではピンクやパープルなど鮮やかな色が若年層に好まれる反面、過度な原色使いは敬遠される傾向があります。ターゲット層に合わせて配色も調整しましょう。
ナビゲーションはシンプルに
韓国流のミニマルデザインに合わせ、メニュー構造や導線もできるだけシンプルにします。ユーザーが迷わず直感的に操作できるUIが理想です。カテゴリ分けは明確にしつつ、トップ画面には必要最低限のメニューだけを置き、二層目以降で詳細を展開するなど、段階的に情報を開示する設計が有効でしょう。
パンくずリスト(現在閲覧中の場所を示す表示)なども、スマホでは隠しメニューにするか簡略化するなど、画面を圧迫しない工夫が大切です。また、日本では一般的でも韓国のユーザーになじみが薄いUI要素は再検討します。例えば、日本発のサービスで見られる独特なアイコンや用語は、必要に応じて韓国ユーザーになじみ深いものに置き換えた方が親切です。
ローカルプラットフォーム連携
NAVERやKakaoとの連携は韓国展開ではほぼ必須と言えます。具体的には、会員登録やログイン時に「NAVERアカウントでログイン」「Kakaoアカウントでログイン」といったソーシャルログイン機能を実装すると、現地ユーザーのハードルが下がります。韓国の他サービスでもNAVER・Kakao認証で利用できるケースが多く、ユーザーはID/パスワード入力の手間なくワンクリックでログインできることを期待しています。
また、Kakao Talkによる通知(チャットボットや友だち追加による情報配信)など、現地で普及しているプラットフォームを活用したUXも検討しましょう。日本企業のECサイトでも、韓国向けにはNAVERショッピングやKakaoのミニアプリに出店したり、公式SNSアカウントでカスタマー対応したりといった取り組みが増えています。UI/UX設計段階からこれら外部サービスとの接点を組み込んでおくことで、スムーズな利用体験を提供できます。
多様な決済手段の導入
韓国はキャッシュレス決済が非常に進んだ社会で、消費者は多彩な電子決済に慣れています。キャッシュレス決済比率は95%以上との統計もあり、クレジットカードはもちろん、Naver PayやKakao Payといった独自の電子マネーで支払えることが当たり前と考えた方が良いでしょう。実際、多くの韓国ECサイトやアプリではこれらのボタンが並んでいます。
日本企業のサービスでも、韓国向けに展開する場合は決済代行を通じてNaver Pay・Kakao Payに対応することが強く推奨されます。チェックアウト(決済)ページのUIには、それらロゴを分かりやすく配置し、ユーザーが使い慣れた方法でスムーズに支払いを完了できるようにします。決済手段のローカライズはUX向上に直結する重要事項です。
安心感と信頼を与えるUX
初めて利用する海外ブランドに対して韓国のユーザーは慎重になることもあります。UI上で信頼性を高める情報提供も忘れないようにしましょう。例えば「正規代理店保証」「韓国XX省認証取得済み」など該当するものがあれば明示したり、レビュー評価やSNSでの高評価を掲載したりするのも効果的です。返品ポリシーや問い合わせ先を分かりやすく表示することもユーザーの安心感につながります。
デザイン面では、過度にポップで軽い印象にし過ぎず、適度に信頼感や高級感を演出することも大切です(特に取り扱う商材が高額な場合やB2B向けサービスの場合)。韓国語で丁寧かつ誠実なトーンのテキストを書くこと、そしてユーザーからの質問やクレームに迅速に対応できる体制を敷くことで、ユーザーとの信頼関係を築けるでしょう。
以上のポイントを踏まえてUI/UXを設計すれば、現地ユーザーに寄り添った使いやすいサービスに近づきます。それでは、実際に韓国市場で成功している日本企業の事例から、具体的な戦略を学んでみましょう。
4. 日本企業による韓国UI/UXローカライズ成功事例
最後に、韓国市場で成果を上げている日本企業の具体的な取り組みを紹介します。ユニクロ、資生堂、一蘭という業界もターゲットも異なる3社が、それぞれ韓国のユーザーに合わせてどのような工夫を凝らしているのかを見てみましょう。
ユニクロ:グローバルブランドのシンプルさと韓国トレンドの融合

日本発のファストファッションブランド「ユニクロ」は、2005年にソウルへ初出店して以来韓国全国に店舗網を広げ、現在では約132店舗を展開するまでになっています。一時は日韓関係の悪化に伴う「ノージャパン」不買運動の標的となり、2019年から2020年頃にかけて大幅な売上減と店舗閉鎖に見舞われました。しかしその後、商品戦略とブランディングの見直しによって韓国市場での地位を回復しています。
ユニクロ成功のポイントの一つが、現地のトレンドに合わせた商品展開とマーケティングです。日本発のシンプルで高品質なデザインは維持しつつ、韓国の消費者ニーズに合わせて細やかなローカライズを行いました。例えば、韓国の若者に人気のあるデザインコラボや限定コレクションを積極的に投入し、「今このデザインが欲しかった!」と思わせる企画を次々と展開しています。
実際、世界的デザイナーブランドとコラボした新商品を発売した際には店舗に長蛇の列ができ、即日完売が相次ぐなど大きな話題を呼びました。また一部の商品は韓国限定モデルやサイズ展開を用意し、体型や嗜好に合うアイテムを提供しています。例えば冬季には韓国限定カラーのフリースや、日本未発売のデザインTシャツが登場することもあります(これらは韓国消費者だけでなく逆に日本のファンから注目されることもあります)。
UX面でも、ユニクロは韓国向け公式オンラインストアやモバイルアプリを整備し、ローカルな決済・配送ニーズに応えています。韓国版サイトでは韓国語による丁寧な商品説明やレビュー表示に加え、ネイバーID連携ログインやネイバーペイでの支払いといった現地仕様を取り入れ、ユーザーが使い慣れた環境で買い物できるよう配慮しています。
また店舗とオンラインの垣根を越えたサービス(店舗受取りや在庫検索など)も導入し、スマートフォン一つで完結する便利さを提供しています。ユニクロの例からは、ブランドの強みを活かしつつ韓国の流行・消費者習慣に合わせて柔軟に戦略を調整することの重要性が読み取れます。
資生堂:現地ニーズに合わせた製品開発とデジタルマーケティング
日本を代表する化粧品メーカー「資生堂」は、韓国でのブランド展開において非常に巧みなローカライズ戦略を展開しています。韓国の美容市場はK-Beautyブームに象徴されるように競争が激しく、国内ブランドが圧倒的な強さを持つ中で、資生堂は日本発ブランドとして存在感を発揮しています。その鍵となっているのが現地消費者の徹底研究とそれに基づく商品・プロモーション戦略です。
資生堂はまず、韓国人女性の肌質や美容ニーズの特徴を深く理解し、韓国市場向けに製品ラインナップや処方を最適化しました。例えば、日本では人気でも韓国の気候や肌には合わない可能性のある製品については、テクスチャーを軽くしたり香りを抑えたりといった調整を行っています。また韓国で特に需要の高い機能(美白ケアや高いUVカット効果など)を盛り込んだ商品を投入し、現地で不足しているニッチを埋める戦略も取りました。
さらに、パッケージデザインやカラー展開でも韓国のトレンドや好みに寄せる工夫をしています。例えば韓国ではカラフルで可愛らしいパッケージが好まれる傾向がありますが、資生堂は高級感を保ちつつもポーチに入れて持ち歩きたくなるようなお洒落なデザインを採用するなど、細部までローカライズにこだわっています。
マーケティング面では、SNSとインフルエンサーを最大限に活用してブランド認知を拡大しました。資生堂は韓国で人気の美容インフルエンサーやビューティーユーチューバーと積極的にコラボレーションし、新商品のレビュー動画やメイクアップ企画を発信しました。またInstagram上でハッシュタグキャンペーンを展開し、ユーザー参加型のプロモーションで口コミを醸成しました。
韓国の消費者はインフルエンサーの推薦に敏感であるため、信頼性の高い美容ブロガーに製品体験を書いてもらうことは大きな効果を生みました。さらに、現地の百貨店やコスメ専門店で期間限定イベントやポップアップストアを開き、直接手に取って試せる機会を増やすことでブランド体験を浸透させています。
これらの取り組みにより、資生堂は韓国市場での認知度・信頼度を着実に向上させ、ロイヤルユーザーを獲得することに成功しました。資生堂の事例から学べるのは、ターゲット層のニーズをとことん研究し、それに合わせて製品開発から販促まで一貫して現地化する重要性です。単に日本の商品をそのまま持ち込むのではなく、「韓国のお客様のための資生堂」としてローカル目線でブランドを構築したことが成功要因と言えるでしょう。
一蘭:日本の食体験を韓国向けにアレンジ

福岡発祥のとんこつラーメン専門店「一蘭」は、日本国外では米国や香港に進出していますが、韓国ではまだ常設店を構えていません。しかし韓国でもその知名度は高く、2024年10月にはソウルの大型商業施設「The Hyundai Seoul」にて初のポップアップストア(期間限定出店)を開催しました。
韓国は1人あたりのインスタントラーメン消費量で長年世界上位(2022年時点で世界2位)を誇るラーメン大国であり、日本の有名ラーメンへの関心も非常に高いため、一蘭の登場は現地ファンから熱い注目を集めました。

このポップアップ出店に際し、一蘭は韓国の顧客に本場の味とユニークな食体験を提供しつつ、現地向けのアレンジも加えました。提供メニューは看板商品の「一蘭ラーメン(博多細麺ストレート)」を中心に据えつつ、日本から持ち込んだ材料でスープを再現し、豚骨ラーメンの本格的な味を韓国で楽しめるようにしました。
一方で、味の調整にも工夫があります。たとえば一蘭といえばトッピングの赤い秘伝のタレが特徴ですが、韓国ポップアップでは通常の秘伝ダレではなく特製の「旨辛コク増し」ソースを使用しています。これは一蘭が開発した新しい辛味調味料で、ただ辛いだけでなくコク深い旨味が加わったものです。韓国のラーメン好きは辛い味にも馴染みがありますが、単調な辛さより旨味のある辛さが好まれることを踏まえ、現地向けにこのソースを採用したと考えられます。
さらに一蘭は、日本でおなじみの「味集中カウンター」(一人ひとり仕切られたカウンターで食事に集中できるスタイル)をポップアップ会場に再現し、韓国の来場者に独自の食体験を提供しました。この仕組み自体は日本と同じですが、韓国では初めて目にする人も多く、新鮮で面白い体験として受け入れられました。
「他人を気にせずラーメンに集中できる」という一蘭流のUXは、その斬新さでSNSでも話題になりました。また、会場では韓国初販売の商品や韓国限定ノベルティグッズも用意され、おみやげ需要を喚起するとともに現地ファンのコレクター心もくすぐりました。例えば一蘭特製のとんこつスープをアレンジしたインスタント商品や、韓国限定デザインのどんぶり、グッズ類が販売され、多くの来場者が購入していったようです。
このように一蘭は、日本のオリジナルな価値(味と体験)をしっかり伝えつつ、韓国のお客様向けに味付けや商品構成をローカライズするバランスを取りました。まだ常設店舗こそありませんが、今回の成功を受けて将来的な本格進出も期待されています。
一蘭の事例からは、飲食業でもUI/UX——ここでは店舗体験やメニュー構成——を現地文化に合わせることが重要であると分かります。味そのもののクオリティは普遍的な強みですが、「現地でどう提供するか」を工夫することでより受け入れられやすくなる好例と言えるでしょう。
5. まとめ
日韓のUI/UXデザイン比較から見えてきたのは、「ユーザーに響く体験を作るには、その土地の文化・習慣を深く理解すること」の大切さです。日本企業が韓国市場で成功するためには、単に日本で成功したデザインや機能を持ち込むだけでは不十分で、現地ユーザーの期待に沿った細やかな調整が求められます。韓国流デザインのキーワードは「ビジュアル重視・モバイルファースト・トレンド即応・ローカル最適化」に集約されるでしょう。
本記事で紹介したように、すでに韓国で成果を上げている企業はデータとユーザー理解に基づいてUI/UXをローカライズし、自社の強みと現地ニーズを上手く融合させています。ユニクロはシンプルさとトレンド対応を両立させ、資生堂は商品もプロモーションも徹底的に韓国向けにチューニングし、一蘭は日本発の体験を崩さずに味や提供方法を現地向けに工夫しました。それぞれアプローチは異なりますが、「ユーザー目線での最適化」という点では共通しています。
誤った情報や思い込みに基づいた戦略ではなく、実際の調査や信頼できるデータ(KOTRAやJETROのレポート、現地消費者の声など)に裏打ちされた判断が重要です。幸い、韓国の消費市場に関する情報源は充実しており、KOTRA(大韓貿易投資振興公社)やJETRO(日本貿易振興機構)からも様々なレポートが公開されています。それらによれば、韓国はモバイル決済やライブコマース、オムニチャネルといった分野で世界をリードする先進的な市場でもあります。こうした最新動向をキャッチアップし、自社サービスに取り入れていく柔軟性も求められるでしょう。
最後に強調したいのは、韓国で成功するUI/UXデザインとは「韓国のユーザーに愛されるデザイン」であるということです。当たり前のようですが、この視点を持つことが何より肝心です。日本流を押し付けるのではなく、かといって迎合し過ぎて自社の良さを失うのでもなく、双方の良さを取り入れたハイブリッドな発想でデザインを作り上げてください。本記事の考察や事例が、そのヒントとなれば幸いです。韓国進出を目指す皆様が、現地ユーザーにとって価値ある素晴らしいUI/UXを実現できることを応援しています。
参照ソース一覧
統計・調査データ
- 韓国のEC市場:成長要因と将来のトレンド – LIFE PEPPER
- ユニクロ店舗数データ – ファーストリテイリング
- 韓国キャッシュレス決済比率 – 野村総合研究所レポート
- 韓国インスタントラーメン消費量 – 世界ラーメン協会(WINA)
企業・事例関連
マーケティング・デザイン資料
公式機関レポート
- KOTRA(大韓貿易投資振興公社)「韓国EC市場と日本企業の機会」
- JETRO(日本貿易振興機構)海外レポート「最近の日韓経済関係」
- 韓国統計庁「EC化率・モバイル利用統計」
- 世界ラーメン協会(WINA)「国別インスタントラーメン消費量統計」